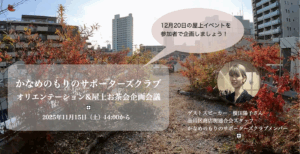第2回オリエンテーションツアー&プレゼンイベントを開催しました。
11月下旬並みに気温が下がり、冷え込む日も出てきました。かなめのもりの木々も少しずつ色づき、地面には大きなコナラのドングリが落ち始めています。
2025年10月18日(土)、第2回オリエンテーションツアー&イベントを秋晴れのもと開催しました。今回は午後に開催でした。行楽日和、運動会シーズン、イベントが各地で盛りだくさんの中にも関わらず、かなめのもりを目掛けてお越しくださいましたみなさま、ありがとうございます!
このオリエンテーションは、サポーターズクラブにご興味を持った方が
・かなめのもりでどのように過ごすことができるだろうか?
・かなめのもりでどのような学びを得られるだろうか?
のイメージをもってもらったり、知ってもらうために、2026年春頃まで、毎月第3土曜日の緑の先生お手入れの日に無料開催しています。
第2回はかなめのもりを歩いてご案内をするだけでなく、緑の先生・稲村純一さんの剪定ミニレクチャーも。そしてPeatixでご案内したように、東京・代々木上原でアーバンシェアフォレスト「コモリス」という活動を主宰している小田木確郎さんによる、都内で緑地を広げる取り組みのプレゼンテーションをしていただきました。
コモリスでは毎週末代々木上原でのお茶会やイベントを開催したり、お手入れWSを行ったりしているのですが、かなめのもり見学を活動そのものに充てて、メンバーの方が多数ご参加くださいました。
小田木さんと共同代表をつとめる南部隆一さん、渡辺英暁さんもお子さん連れでお越しくださいましたほか、インフラ・通信関係、技術畑の方、植物に関わる事業経営者、デザイナー、編集者などなど、さまざまな職種の方とともに充実した時間を過ごすことができました。
前回のご案内からサポーターズクラブにご登録くださったみなさまも。少しずつかなめのもりの魅力を伝えたい!と思ってくださる方の輪が広がっていくのがうれしいです。
では、さっそく当日の様子を写真でご紹介します。

まずはかなめのもりのビル2階、フリースクール前の庇にあたってしまった樹木や、混んでいる下枝をどのように剪定するか、その考え方、視点を稲村先生が解説。背後の剪定済みの植栽と比較しながらの解説はわかりやすかったです。

屋上へ上がるとみなさん口々に、「これが3年目!」と驚きの声が上がりました。

さっそく剪定実習。品川区商店街連合会の榎田陽子さん、そして公共R不動産のプロジェクトに関わる梶田裕美子さんも剪定バサミ持参で参加してくださいました。

枝が向かおうとしている方向と通路の関係、隣り合っている樹木とあたっていないか、などなど全体をみながら、混んでいるところ、風通しの悪そうなところを見て選定していきます。「迷ったら切らずに様子を見て」という稲村先生のことばに頷く参加者さん。

屋上から1階のかなめのもり稲荷神社へ。初代・長谷川要之助の名前の一字をとってかなめのもりという名前をつけた商業ビルで、創業時から変わらない一角がこの神社周辺の土地。その意味を参拝後に代表の井上創社長から解説してもらいました。

プレゼンの前に、この建物が建設されたプロセスを解説。みなさんからは防水、耐荷重をはじめ、下地のつくりかたについて次々質問が飛び出しました。

小田木さん(左)のプレゼン後、かなめのもりとコモリスに関する質疑応答タイム。
質疑応答の内容が気になる方も多いと思いますので、長くなりますが、本文の最後にご紹介しますね。
14:00に集合してから、質疑応答、ご感想をいただいて、サポーターズクラブにご登録手続きをされてお帰りになるまで17:30まで! 長時間にわたってご参加いただきましてありがとうございます! 途中予定があってやむなく退席された方も、お子さん連れの方も楽しんでいただけたでしょうか?
かなめのもりではサポーターズクラブにご登録いただいた方に、その場で屋上まで上がることのできるカードキーご登録をさせていただいています。現在年会費3,000円で受付中。パスモ・スイカカード(スマホもOK)に情報をご登録しますので、平日9:00−17:00まで屋上に上がることができます。
かなめのもりのビル屋上は普段は立ち入りができません。いわばサポーターズクラブにご登録いただいた方だけのスペースです。
今回のように毎月第3土曜日に屋上への上がり方やカードキーでの入退室、屋上で過ごす上での注意事項をお伝えしますので、ぜひオリエンテーションイベントにご参加くださいね。クレジットカードでお支払いいただけましたらその場でカードキー登録をいたします。
来月は11月15日午後開催予定。都内有数の品川区商店街の環境への取り組みについてのお話しがあります。
ぜひ楽しみにしていてくださいね。
質疑応答
Q1 かなめのもりでは生物多様性の指標、データ化はどのようにしていますか?
A1
かなめのもり・井上:3年前の竣工時は、ポット苗で植えた樹種が20−30種類でした。2年目に生態調査を行った時は約90種まで増えていましたので、多様性は少なくとも3倍近くになったと言えます。
Q2 かなめのもりができて、周囲(主に近隣住民)からの反応はどのようなものがありましたか?
A2
参加者でご近所お住まいの方 Kさん:20年来の住民です。武蔵小山にはこれからタワーマンションが3棟も建つ計画があります。そのような中でここが建設されている時から気になっていて、できあがったらこのような森ができあがり、誇りになりました。志を持ったオーナーが小さなことからできることを市民に示す機会として、サポーターズクラブができてとてもハッピーです。
参加者でご近所お住まいの方 Eさん:団体の環境啓発をしています。このかなめのもりはあり方自体がそのほかの施設とは違っていて、新たな取り組みができたと感じています。心から応援できる場所ができて、ありがとう、という気持ちです。
かなめのもりの管理人 Yさん:出来上がる前は「木が飛んでこないか?」「虫が飛んでこないか?」という声も寄せられたように、正直良い意見だけでなく悪い意見(心配)もあります。
今は歩行者の方から「気持ち良い環境になったね」と言われるのがうれしいです。
Q3 行政を巻き込みながら、市民が緑地の手入れをしている事例があれば知りたい。
A3
コモリス・小田木さん:世田谷区南烏山公園。行政と区民が連携しながら区民主体で管理を行なっている。
事務局・小川:世田谷区は「みどり33」という部署があり、2030年までに区の面積の33%を緑地にすることを目標に掲げ、区が積極的に土地を買い上げて公園や緑地とすることを政策に掲げている。現在進行中の代沢せせらぎ公園も、区がランドスケープ設計会社に依頼し、区民の声をワークショップで集約しながら設計に反映するなど、民意の吸い上げ方を工夫している。
Q4 コモリスのメンバーの顔ぶれが知りたい。
A4
コモリス・小田木さん:1期募集でメンバーは15名、2期募集で25名になりました。オンラインを含めて50名近くのメンバーが登録しています。若い世代は、遠く信州大学から通っている大学生のほか、犬のおしっこポールを開発した慶應SFC生など。30−40代の大企業に勤めている方のほか、50代、大学教授などが参加してくれています。
課題は地域(地元)にどう広げるか、です。
Q5 かなめのもりでは地域の方がどのように関わるビジョンを持っていますか? オープンデイの予定はありますか?
A5
事務局・小川:2026年4月までオリエンテーションツアーを毎月第3土曜日に無料開催します。11月15日(土)は品川区商店街連合会の方から環境に関するお話を、12月20日(土)は11月15日に企画会議を行なって、お茶会を開催する予定です。
Q6 かなめのもりの緑地の維持管理で一番苦労していることは?
A6
かなめのもり・井上:見学に来られる方からの質問で多いのは、コンクリートが割れたところに根が入らないか、ということです。80年以上の耐久性が想定できるコンクリート地盤の上に、浸透するグリ石層の地盤をつくって、植物の根がマウンドから横方向に這うように設計しています。天井の懐も1メートルあって、万が一漏水があったら点検口から対処ができるので何ら問題はありません。私はオーナーなので、自分で責任を取ることができる。何かあったらと懸念が出た時に責任を取れるのはオーナーとディベロッパー。私は、問題はその覚悟がオーナーにあるかどうかだけだと思います。
例えば森ビルさんは地下通路を緑化する事例をつくっていますね。
確認申請や手続きの際に前例を行政から問われることは想定内。このビルは都市で緑化をしたい、本物の森をつくりたいと思ったオーナーやディベロッパーにとって前例となろうと思ってつくったのです。
Q7 このモデルで展開しにくいことは?
A7
かなめのもり・井上:一般化はしにくい。愛情をもった人を探せば可能では。
Q8 (緑の先生ふたりに)かなめのもりの現場施工で苦労したことは? 逆に良かったことは?
A8
緑の先生・稲村さん:苦労したことはグリ石のこば立てがすべて手作業だったこと。良かったことは、ずっと将来も残るやり方(施工方法)だとわかったこと。正直、人工地盤上で3年でこんなに森が育つとは思わなかった。
緑の先生・南川さん:苦労したことは人海戦術だったこと。逆を返せな丁寧に仕事ができたことは貴重な経験だった。
Q9 当初想像していなかったけれども、好例として展開できること。
A9
緑の先生・稲村さん:屋上緑化の恒例になると思います。このビルの設計者でもある川島範久建築設計事務所の案件で応用しています。工法は比較的シンプルなので、駐車場地盤にも応用できます。